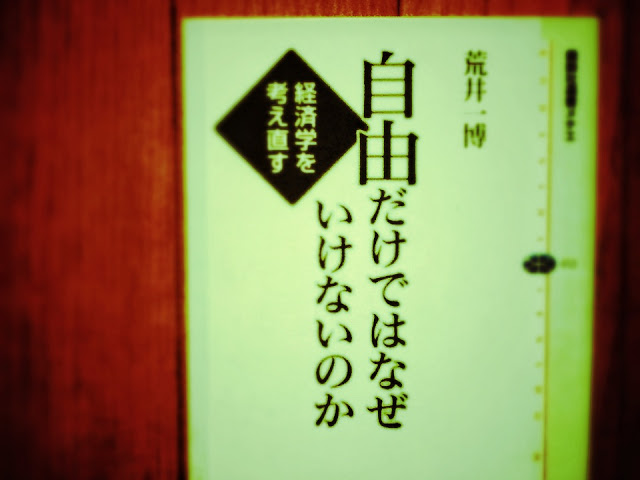
自由だけではなぜいけないのか ~経済学を考えなおす~ 荒井一博
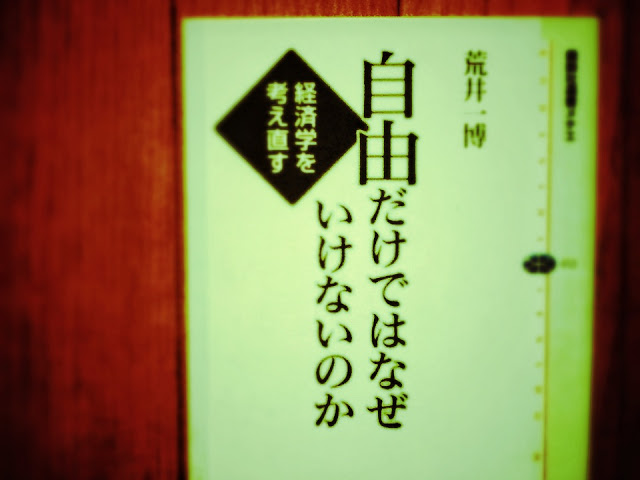 |
| 自由だけではなぜいけないか 荒井一博 |
Ⅲ, 個人の独立性という虚構
■「関係ない」という価値観
今日の小学生以上の日本人の多くが、「関係ない」という言葉を頻発したり、「関係ない」ことを強く意識して行動したりしているようです。この言葉は、問題となる特定の他者(あるいはそれに関連する事柄)と自分とは無関係であって、自分はその他者から独立しているという主張を含意します。かつては関係ないという言葉を今日のような意味で使う人があまりいませんでした。
これほど明確に新古典派経済学の浸透を象徴する言葉も少ないでしょう。すぐ後で検討するように、同経済学の個人の間には実質的に何の関係もなく、各人が独立しています。それと同様なことを10歳前後の子どもでも訳知り顔に口にしているのです。しかし、本書でこれから次第に明らかにするように、「人間が独立している」あるいは「人間が独立していられる」という新古典派の考え方は完全な虚構であるだけではなく、きわめて深刻な問題を生み出す原因になります。
関係ないという価値観を持つ子どもに、他者や社会一般に対する配慮を教えることはきわめて困難です。かつての学校教育は「社会に貢献できる人間になれ」と説いたものですが、関係ないと考える今日の生徒にそのようなことを説いても、馬耳東風となるだけでしょう。関係ないという考え方の誤りを正確に理解するにはゲーム論の知識が必要で、本書でも後で簡単なゲーム理論的考察を導入してみたいと思います。
関係ないという表現は自他の間の距離感を広げ、挨拶・援助・互助・社会貢献などの人間関係を拒否するための口実に使われています。あるときは、自分が他者にかける迷惑を正当化する役割も果たします。「お前は俺と関係ないから俺に文句をいうな」というような思考法です。他者を利用してから縁を切る際に使われることもあります。
独立性と自由はコインの裏表の関係にあります。個人の独立性が低ければ、自由な行動は困難になるからです。そのため、自由主義はかならず独立性の重要性を強調します。そして自由主義教育では「独立した個人」の育成が基本になります。
独立性を強調するこうしたイデオロギーは、個人を煩わしい義務感から開放し、連帯を希薄化する機能を果たします。特に共同体や連帯を破壊します。自由主義の基本的な目的の一つは伝統を破壊することですが、個人の独立性の強調は伝統的に形成された共同体を破壊する強力なコンセプトになるのです。実際のところ、個人の独立性が強調されるにしたがって、わが国の共同体は急速に消失しました。また、個人の独立性の考え方は家族の連帯感も破壊し、今日の家庭崩壊を促進しています。
■新古典派経済学に表れた個人の独立性
新古典派経済学には個人の独立性の思想が明確に盛り込まれています。なぜなら、その効用関数は個々の消費者が自分で消費する消費財の数量と自分が供給する労働の量のみの関数だからです。それは、隣人や職場の同僚の消費量や労働供給量の関数ではありません。つまり個人の満足感・幸福度は、単消費者の消費や労働供給(他者の満足感)から独立しているのです。
もっと平易に表現すれば、新古典派経済学のなかの個人は、自分の周囲の人達に対して、嫉妬心も慈悲心も感じないのです。自分が粗末な住宅に住み、隣人が豪邸に住んでいても、嫉妬心を抱きません。他方、優雅な生活をしている個人は、貧民街を通りかかっても心の痛みを感じません。さらにいえば、他者が組織や社会でいかに不当に扱われていても何も感じません。公憤も抱きません。これが新古典派の意味する独立性なのです。
新古典派経済学では、企業の生産関数も独立性を有する表現になっています。企業の生産量はそれが投入する労働や原燃料や部品の量のみの関数であって、他企業の投入量や産出量の関数ではないからです。そのため同経済学には、上流の企業が排水を垂れ流して、河口付近の漁業者(企業)が迷惑を被るというような問題がありません。こうした独立性重視の価値観(偏見)を現実の企業が持っていると、一部の国に見られるように、地球温暖化を気にしないで多量の二酸化炭素を大気中に排出するでしょう。関係ないとうそぶいて、実際には他者に迷惑をかけるのと同じ論理です。
なぜ新古典派経済学は個人の独立性を重視するのでしょうか。一つの理由は、極端な仮定を採用して議論を単純化し、明快な結論を得るためです。特に数字を使って思想を表現する場合は、単純な仮定を採用しないと議論が困難になる傾向があります。しかし、それだけが理由ではありません。個人の独立性が西欧社会の伝統的な理想であることが、もう一つの重要な理由です。他者依存は卑屈で独立が高潔であるという価値観の伝統です。神には依存するが人間には依存しないという考え方もその背後にあります。
たしかに、他者に依存しすぎることは卑屈に通じるでしょう。しかし、問題は現実の人間が他者から独立して生きられないことです。また動物には集団を形成して生きるものと、そうでないものとがありますが、ホモ・サピエンスは前者に属し、しかも相互依存の程度が顕著です。西欧人も含めて人間には完全に独立して、すなわち孤立して生きることができないのです。現実の人間は、依存性と独立性を妥協せながら生きていかざるをえません。この認識から出発して人間の生き方を考える必要があります。
■独立性を最大限に保証する場としての市場
新古典派経済学では、効用関数や生産関数が個人の独立性を重視した表現になっているだけでなく、市場でも独立性の保障される取引が行われると仮定されています。それを象徴的に表すのが労働市場なので、まずそれに注目してみましょう。
新古典派経済学のなかの労働者は、特定の会社に従属することがありません。上司から不当な要求をされたり、同僚から嫌がらせを受けたりした場合には、ただちにその会社を辞め、他の会社で同様な仕事ができると仮定されているのです。解雇された場合も同じです。
また新古典派経済学の世界では、組織忠誠心を発揮することや、会社の帰りに同僚と飲みながら仕事の話をすることは、まったく無駄な行為です。そのようなことをしても生産性は上がりません。前述のように、企業の生産関数は所与で、生産量は市場で購入可能な投入物の量のみに依存するからです。労働市場で評価される能力が同等の労働者は代替可能なので、連帯感は必要ないのです。新古典派経済学の浸透とともに、組織忠誠心や職場の連帯感が希薄化してきたのは自然な成り行きといえましょう。同経済学の個人は組織に縛られることなく、自分のことだけを考えていればよいとされているのです。
右の論点を少し敷衍(※フエン・押し拡げること)しておきましょう。新古典派経済学には多数の企業が存在して、労働者は無費用で企業間を移動できることになっています。少しでも有利な条件の企業があれば労働者はそちらに移動し、少しでも不利なことに直面すれば在職する企業を辞めて他企業で働きます。こうした状態にある労働者は、特定の企業(他者)に依存することなく生きることができます。ほとんど仮定からして、こうした世界では職場の人間関係に起因する悩みなどありません。
それに対して現実社会の労働者が上司の「不当な」要求に従って働かざるをえなかったり、同僚との人間関係に苦しめられたりするのは、他企業で同等な仕事に就くことが容易でないからです。こうした状況にあれば、他者から独立して生きていくことができません。
このことは現実の他の市場を考えてもはっきりします。多くの日本人は野菜・アイスクリーム・石鹸などを購入する時に、小売店の主人や店員の機嫌を損ねないよう特に気をつけていないでしょう。その理由は、他の多くの小売店でもそれらを同様な取引条件で購入できるからです。一つの小売店からしか購入できなければ、特別丁寧な挨拶をしたり、場合によってはプレゼントを持参したりする必要が生じるはずです。このように、市場で多数の代替的な取引機会が与えられていることが個人の独立性を保証しているのです。
■西欧文化と市場
新古典派経済学のなかの個人は高い独立性を有し、市場以外で関係をもつことがありません。また、市場において個人と個人は市場価格のみによって関係づけられており、個人間に直接的な関係がありません。個人は自分が取引したい財の価格を観察して、その価格で望む量の取引を行うだけです。これが新古典派経済学のなかの人間関係で、図3-1のように図示することができます。例えば個人Aと個人Bが取引する際には、すでに決まっている市場価格を通して(受け入れて)、各自の望む数量を売買するのみです。
市場自体も、われわれが現実経済で観察するものとだいぶ異なります。新古典派経済学のすべての市場には(暗黙のうちに)競売人がいると想定されていて、彼が需要量と供給量を一致させるように価格を決めます。こうした事態は現実の労働市場やサービス市場やパソコン市場と明らかに異なります。競売人のいる現実の市場は例外的です。
図3-1に示された人間関係は、一神教の世界で神が個人の関係を規定する上体に酷似しています。その世界の個々人は、共通の神を媒介として人間関係を維持することになっています(そのため、神を介して関係を持った人間を裏切ることは、神を裏切ることになると考えられているはずです)。市場では剤の市場価格が神の役割を果すのです。アダム・スミスの「(神の)見えざる手」という表現は意味深長であるように私には思われます。
過去数百年の間に、西欧は市場を重視した人間関係を樹立してきました。それが個人の独立性を重視する西欧文化とかなり整合的であったためと考えられます。自由主義や今日の米国人の考え方には、取引を市場に任せておけば、特定の個人に隷属しなくても良いという期待があります。また、個人所得の上昇などとともに個人の独立性が以前より重視されるようになると、市場を使った取引が歓迎される傾向も生じてきます。
しかしそうした意図や思考に反して、現実の労働市場のように代替的機会が限られた市場では、個人の独立性はあまり保障されません。その証拠に、欧米人でも解雇を通告されればかならず怒ったり、あるいは落ち込んだりします。米国では解雇されたものが乱射事件を起こしてメディアで報道されることもあります。労働市場などの現実の市場は明らかに新古典派経済学の世界と異なります。個人の独立性は西欧の理想ですが、実現できない場合が多いのです。
それだけでなく、たとえ実現可能であっても個人の独立性をあまり重視すると、組織などの効率性が低下するという問題もあります。個人の独立性が精神的には好ましいとしても、生産性の点では劣ることがあるのです。本書ではその点も詳しく検討します。
■文科省の教育方針にも影響
文部科学省の審議会でも、独立性と類似する概念である「自主・自立」の価値が頻繁に強調されていることが、その議事録よりわかります。新しい政策や提案は、それが子どもの自主性や自立性の育成に寄与するということで正当化されているようです。換言すれば、文科省も「自主・自立」という価値の教育を通して、個人の独立性を強く支持していることになります。また、その効果が実際に現れつつあるともいえましょう。
=
何をするのも自由だと考える若者を教育することは困難だからです。自分に不十分なところがあると認識し、教師や親に従う意志のあるものでなければ、真の教育は受けられません。
=
独立性重視が金銭欲を強める
独立性を重視する価値観が社会を支配するようになると、人々の金銭に対する志向が強くなります。米国社会は個人の独立性を重視する典型的な社会ですが、その一方で金銭至上主義の文化を持つ社会でもあります。
=
多くの経済学者さえ明確に理解してないと推察されますが、新古典派経済学は個人の行動に関してある種の極めて厳しい倫理的制約を課しています。「法と契約を完璧に遵守する」という制約です。同経済学の中の個人は、法と契約を守るという意味では完璧に信頼出来る倫理的な人間なのです。新古典派が問題とする倫理は法と契約の尊守だけで、それ以外に倫理はありません。例えば、他者に対する配慮や社会のための自己犠牲や陰徳は同経済学と無縁な概念です。他方、合法的であればどのようなことを行なっても非難されないことになります。そのため、そうした思想が浸透すると通常の意味での倫理は消滅していきます。
==
法律万能の社会で争いや個人間のトラブルが生じたら、裁判によって解決することになります。しかし、個人が裁判を利用すると多額の費用を負担しなければなりません。弁護士費用や自分の時間的・心理的費用などです。
=
これに関して恐ろしいのは、私が「司法のパラドックス」と呼んでいる現象です。全ての争いは方に基づいて解決されるべきであるという社会通念が形成されると、裁判に訴えられない行為は全て正当であると見なされるようになります。すると右記のように裁判費用を下回る被害を生み出す不正は、実行しても訴えられないので正当と見なされ、日常的に発生するようになります。裁判に訴えられないと踏んで、他者に積極的に害悪を与えて自己利益を得る合理的個人が多くなるからです。
=
個人の私利追求を奨励して経済の効率化を図ろうとすることは、各人の好みを絶対視することでもあります。各人の好みは合法的である限り尊重し、それを基準にして各種の判断を行う考え方です。ここで再度強調すれば、各人の好みがどのようなものでどのように形成されたかを新古典派経済学は問いません。この倫理に従えば、一般に多くの好みを満たすことは善となります。多くの人が需要するものを供給することは、社会に大きく貢献すると見なされるのです。新古典派経済学は基本的にこのような哲学を持っています。
=